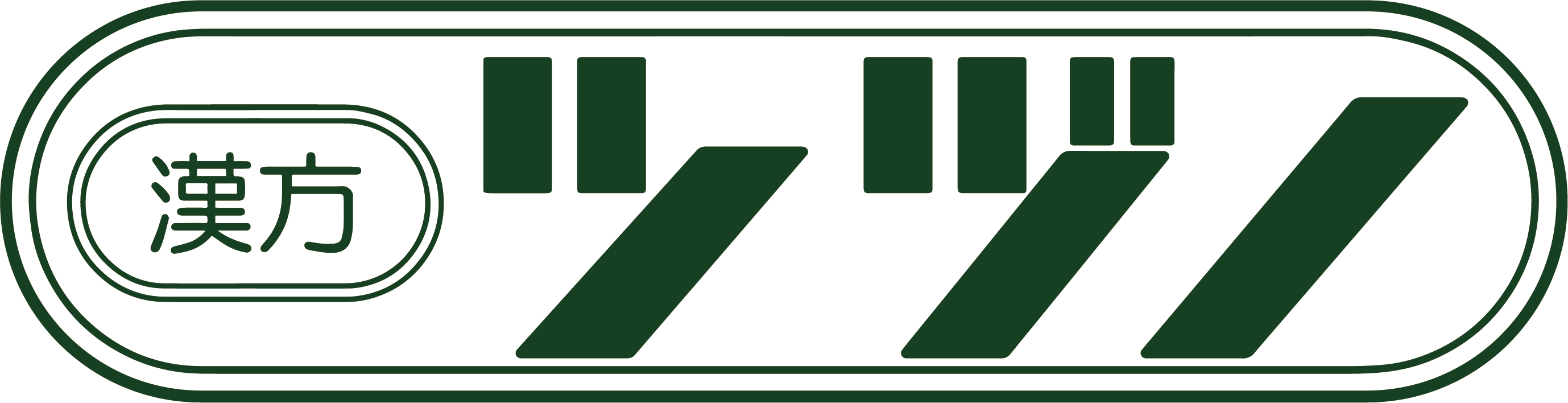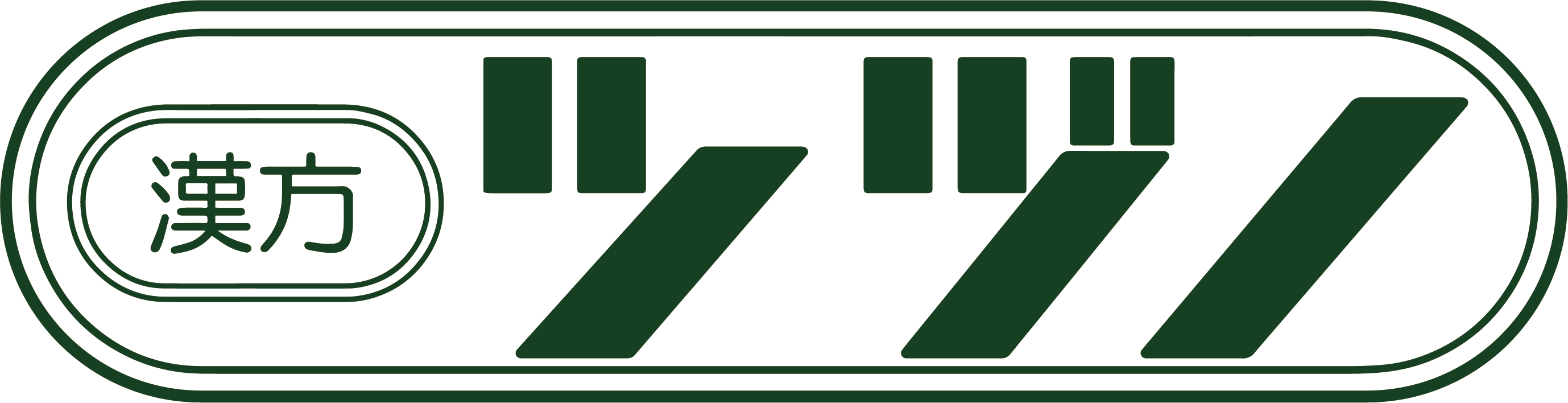LINEで簡単ご予約/相談

漢方では『冷え』は気虚(ききょ)をまず考えます。
気虚(ききょ)
気虚とは?
漢方において、身体を維持・活動させるためのエネルギーである「気」が不足している状態のことを指します。
気虚の症状
気虚になりやすい人の特徴は、職場や家庭でストレスを強く感じている人、胃腸が弱い人、過労ぎみの人、食生活が乱れている人などが挙げられます。気虚の症状には次のようなものがあります。
- 疲れやすい、だるい
- 元気が出ない
- 気が落ち込みやすく、やる気がでない
- 日中眠くなる
- 汗をかきやすい
- 食欲不振
- 生理周期が短くなる、月経血の量が多くなる
- 手足など身体が冷える etc.

気虚の原因
気虚の原因としては、次のようなことが考えられます。
- 胃腸の機能が低下して、食べ物からエネルギーを取り入れることができない
- 過労などでエネルギーを使いすぎてしまう
- 過剰なストレス etc.
『気』とは何か?
『気』とは人の原動力とも言えます。
『気』には大きく5つの効果/作用があります。
- 推動(すいどう)作用:全身に栄養を運んだりものを排泄させる力
- 温煦(おんく)効果:体を温める力
- 防御作用:抵抗力や免疫力を差し、外部の敵から身を守る力
- 固摂(こせつ)作用:体の血液や汗などが体から漏れ出ないようにする力
- 気化作用:気から変化して血を作ることができるのですが、このように気から別のものを作る
冷えの原因
冷えの原因の一つとして、気虚による ②の温煦効果(体を温める力)の低下が考えられます。
カラダ全体に気が少ない人は、一般的に「脾」が弱く瘦せている人が多いです。
また、脾が弱い人は食欲があまりなく食べても太りにくい人が多い傾向にあります。
脾(ひ)とは?
西洋医学の脾臓とは異なります。
東洋医学の考え方で、体の機能や働きを五行で分けた五臓(肝・心・脾・肺・腎)のうちの1つ。
消化吸収や栄養の輸送、免疫などに関わる働きを持つ臓器のことで消化器全体を指します。
脾の機能が低下してしまうと、食欲不振、腹痛、下痢、全身倦怠感、むくみなどの症状が現れます。

気虚による冷えの治療

気虚による冷えの根本治療をする場合、脾胃(胃腸)を整え『気』を自力で作ることが出来るようになることが重要です。
ストレスにより気の失調が起こり、冷えを感じる場合
気は性質上、上昇しやすいため上半身はのぼせ、下半身や指先や足先などの末端は冷えを感じます。
改善方法として、ストレスの原因環境を変えたり、休みの日にストレス発散の方法を見つける必要があります。
補気益気•健脾をして改善します。
このような状態の際には、四君子湯(しくんしとう)六君子湯(りっくんしとう)、補中益気湯(ほちゅうえっきとう)レオピンなどの漢方が用いられます。
ストレスからくる冷えの場合
気の停滞を改善する疎肝理気薬を中心に用いて改善させます。
このような状態の際には、四逆散(しぎゃくさん)、加味逍遙散(かみしょうようさん)などの漢方が用いられます。
まとめ
- 冷えの原因は気虚であることが多い
- 体を温める漢方を使って冷えを改善することも出来るが根本的な療法にはなっていない
- 気の失調(ストレス)で冷えを誘発する事もある
- 気虚には六君子湯や補中益気湯など補気益気、健脾する漢方を使う
- 気の失調の冷えには四逆散など疎肝理気薬の漢方を使う
漢方相談前にお問い合わせをされたい方は、
お問い合わせページよりご連絡いただく、もしくは当薬局代表電話(03-3765-5151)まで直接お電話ください。
皆様からのご相談やお問い合わせお待ちしております。
代表取締役社長 廿野 延和 - Tuzuno Nobuyasu –